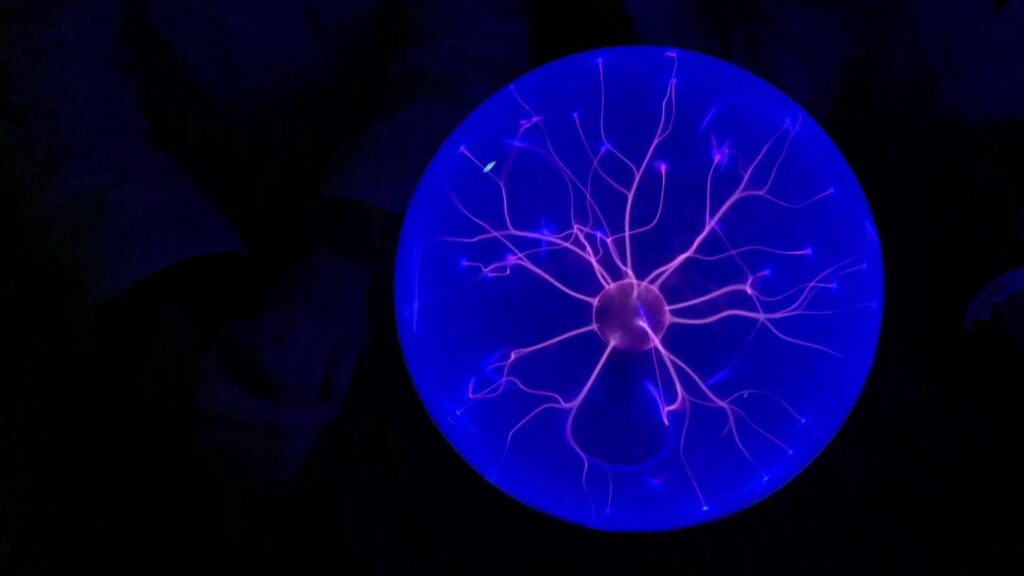前回、かつての日本の子どもたちがそうであったように、現在は発展途上にある国の子どもたちは、ちょっとした素材で目を輝かせ、科学への関心を高めているに違いないということを述べました。彼らは、いずれは科学力によって社会に貢献し、国際社会で一定の力になっていくであろうことは容易に想像できることです。彼らが、日本の今の子どもたちのライバルになっていくのです。というより、もしかしたら発展途上にある国の子どもたちの後塵を拝するようなことになりそうな感すらあります。某大学教員と話題にしたことなのですが、大学の講義で時間前に教室の最前列に着席して、講義内容のすべてをメモし、熱心に聞いては質問する、配布物は余計に持って帰る…のは海外発展途上国からやってきた学生ばかりという話。日本の学生は、最後列で居眠りはするわ、遅れて来たかと思うとこそこそ明らかスマホゲームに興じてる様子…。もちろん、本国の期待を背負ってやってくる留学生と日本の若者をそのまま比較するのはフェアではないことはわかります。ただ、そういうのを目にすると暗澹たる気持ちになり、何かとてつもなく不安な将来が見えてくるわけです。近い将来、日本の若者の多くが海外に渡り、現地の経営者を「ボス」呼ぶ時代がやってくるかもしれません。…次回に続く。